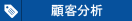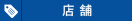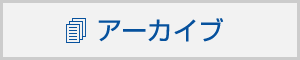顧客情報をつかむツールとしての「アイカード」
(株)伊勢丹がハウスカードである「アイカード」の発行を開始したのは1987年6月。丸11年を経過した現在、口座数にして約100万、家族カードを含めて約145万人の会員を擁する。年会費無料、5%優待でスタートした「アイカード」は、その後数回の見直しを経て、現在は年会費2,000円(初年度は無料)、優待率は前年度の購入金額が20万円未満の場合は5%、20万円以上100万円未満の場合は7%、100万円以上の場合は10%となっている。年会費を有料化し、また、使えば使うほどトクになるシステムを採用したことによってカード利用が促進され、より精度の高い情報が収集できるようになった。カードの稼働率は約70%。平均購入金額は年間20万円を超えているという。
会員データベースには、住所、電話番号、家族構成といった属性データのほかに、過去3年間の購買履歴、ダイレクトメールの送付・レスポンスなどについての情報が蓄積されている。これらのデータは営業本部のほか、店舗に設置された端末からも随時、検索・活用することができる。
商品政策への活用としては、2?7月、8?1月の年2回に分けて会員の購買データを集計・分析。特定の売り場・ショップにどの年代層の顧客が、どのくらいの頻度で来店しているか、それは企画意図通りであるのかズレがあるのかといった検証がなされる。ズレがあるのであれば、MDを見直す、あるいは、実際の顧客層に合わせてショップを適切なフロアに移動するなどの措置が採られる。同社はJANコードによる単品管理に基づくQR(クイック・レスポンス)への積極的な取り組みでも知られているが、これと併せて顧客情報と商品情報をマッチングする「アイカード」会員データを活用することで、より正確な売上予測、緻密な商品政策が可能になるわけだ。
また、販促計画の資料として、4?3月の1年単位でデータを集計。年報としてまとめている。たとえば、どの地域の顧客が、どのくらいの頻度で来店し、いくらの買い物をしているかというデータから、店舗ごとの商圏が明らかになる。これによって、どの地域にチラシを折り込めばよいか、あるいは、誰にダイレクトメールを送れば効果的かがわかる。
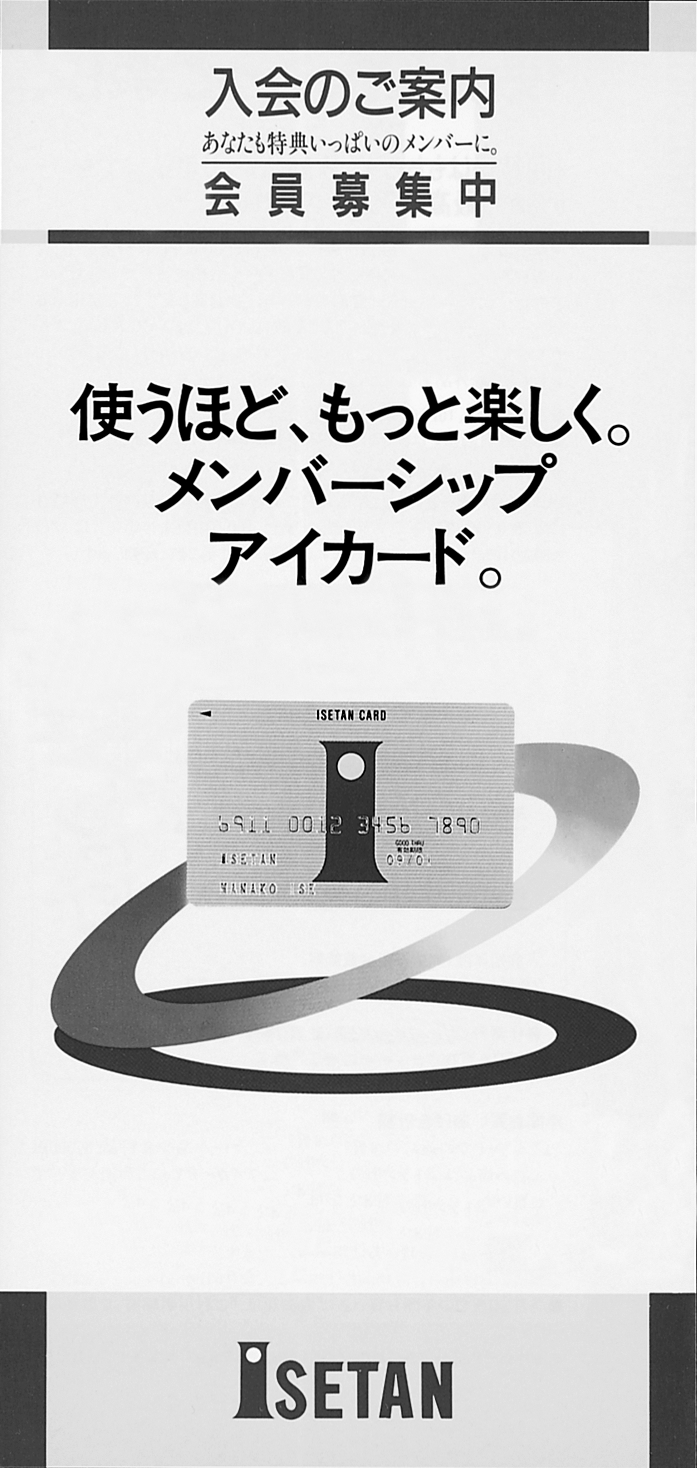

約145万人の属性、および購買データの収集を可能にしている「アイカード」。使えば使うほど、優待率がアップする
現場で使えなければ意味がない
ひとりひとりの伊勢丹ファンのニーズを知り、それぞれに合った商品・サービスを提供することが「アイカード」の目指すゴールである。そのためには、実際に販売に当たる店舗のスタッフが日常的にデータを活用できなければ意味がないというのが同社の考え。日々、顧客と接する中から生まれてくるさまざまなアイディアや仮説を、多面的な切り口から検証することで、顧客情報は生きてくる。システム開発に当たっても、「現場で使える」ことを第一義とした。
同社が取り扱う商品アイテム数は非常に多く、また、ファッション商品であるだけにライフサイクルが短い。加えて商品の企画には長期間を要するため、顧客の購買データを販売予測や商品開発に生かすことは極めて難しい。このため各店舗や売り場では、たとえばMDや催事などの結果検証にこれらのデータを活用しているケースが多い。企画の狙いが達成された、ターゲットに間違いはなかったという科学的な裏付けを得られることが、「店長やセールス・マネージャーの自信につながっている」と同社営業本部 営業政策担当 顧客・カード政策 部長の荻原日出男氏は語る。会員データはほかに、電話やハガキによる催事の案内などにも活用されている。
また、優良顧客が誰かを知ることができるのも、データを一元管理する大きなメリット。通常、販売員は、自分の売り場の優良顧客は知っていても、その顧客が同時にどの売り場の得意客であり、伊勢丹で年間どれだけの買い物をするのかまでは知らない。しかしたとえば、その顧客の好みのブランドを知っていればそれに合う洋服をお奨めすることができるし、必ず食料品フロアに寄って帰る顧客だとわかっていれば、その日の食料品のお買い得情報を提供できる。自分の売り場ではあまり頻繁に買い物をしない顧客でも、伊勢丹の上得意客だと知っていれば、お礼を述べることもできる。顧客情報をもとに、プラスαのサービスを提供することが可能になるのだ。
「我々は必ずしも伊勢丹でしか買えない商品を扱っているわけではありません。伊勢丹ファンを育てるには、いかに質の高いサービスを提供するかが鍵です」(荻原氏)。会員データベースは、これをサポートするツールなのである。
定性情報をとる
同社では「アイカード」会員のほかに、友の会や、各種催事のダイレクトメールを希望する顧客を組織化し、その属性情報を蓄積している。また、商品やサービスの満足度などを把握するために、関連会社の(株)伊勢丹研究所を通して、各店舗ごとに3?5年に一度、アンケート調査を実施している。
そのほか同社では、日々、各店舗の販売員から、顧客情報を収集している。「アイカードによる売り上げは、販売額全体の50%以下。それに購買履歴からわかるのは、結果にすぎません」(荻原氏)。「アイカード」で優良顧客を囲い込む一方で、より多くの伊勢丹ファンを育てるために、ひとりひとりの顧客の声に耳を傾けているのである。
同社では全店数千人の販売員に、顧客の意見・要望を記入するシートを配布している。これには「商品」「サービス」「施設・販促」の3種類がある。販売員が記入したシートは本部に集約され、担当部署に回される。担当者はこれにコメントを記入して、再び販売員の手元に戻す仕組みだ。
たとえば「?という商品をご希望のお客様がいらっしゃいましたが、取り扱っていないのでお応えできませんでした」というシートに対しては、担当のバイヤーが「類似商品が▽▽売り場にありますから、今度同じようなご質問があったらそちらにご案内してください」といったコメントを返す。仮に白いブラウスが100枚売れたとすれば、バイヤーは次回も白を100枚発注しようとするだろう。しかし、「本当は黒がご希望だったけれど、扱っていないので白を購入された」という情報が多ければ、バイヤーは次回は白だけでなく黒も仕入れることで、顧客の満足を高めることができる。また、商品を気に入っていただきながら最終的に購買に結び付かなかった場合には、その理由が記入される。「価格が少々高かった」「襟元のボタンがお気に召さなかった」といった細かな情報がバイヤーに届き、次回のMDに生かされている。
各売り場では、情報収集のテーマを設けるなどして、継続的に顧客の細かな要望を吸い上げる努力をしており、日々、非常に多くの顧客の声が本部にフィードバックされているという。
店舗の主役は顧客。その意味をこめて、同社では売り場という言葉を使わず、“お買場”と呼ぶ。この“お買場”構想は、さまざまなチャネルを活用して収集される顧客情報に裏付けられてはじめて、実現するものなのだ。