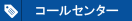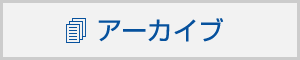顧客にいきなりコールするのではなく、まずははがきやDMを送付して「電話がかかってきそうな雰囲気」を演出する、2ステップが望ましい―これこそ、(株)フタバ化学が試行錯誤の末に得た結論だ。
待ちの姿勢からの脱却
アロエエキスを配合したボディソープをホテル・旅館向けに直接販売し、一般生活者に実際に使用してもらうことでファンを増やしてきた(株)フタバ化学。当初はB to Bのみのダイレクトマーケティングだったが、一般生活者から直接注文が入り始めたことから、1991年にB to Cの直接販売を担当する(株)リーブルを設立。1993年には、B to B、B to C双方のテレマーケティングを行う子会社(株)テレリーブルを設立した。B to B、B to Cともにせっけん、シャンプー、リンスなどのバス用品を取り扱い、顧客数は前者が約7,000、後者が約10万となっている。
今回は、テレリーブルの親会社であるフタバ化学を訪れ、B to B、B to Cにおけるアウトバウンドの概要とコツについて話を聞いた。
現在のコールセンターは、アウトバウンド10ブース、インバウンド5ブースとなっており、どちらの業務もテレリーブル設立とともに開始した。コールセンター開設と同時にアウトバウンドを開始した理由について、取締役・社長室室長・志水美智葉氏は次のように語る。
「コールセンター開設当初は、DMを送付して顧客からのコンタクトを待っていた。しかし、“消費者とともに”を経営理念に掲げるのなら、私どもから積極的にお声がけをするべきと思い、アウトバウンドをスタートさせた。もともとフタバ化学の営業担当者が行っていた訪問による“御用聞き”を、テレマーケティングでも行えるのではないかと考えた」。
一般生活者向けアウトバウンド
テレリーブルが現在行っているアウトバウンドの内容は主に3つある。
まず主業務となるのが、「以前、ご購入いただいた商品はまだありますか」「新しい商品が発売されましたがいかがですか」という御用聞きコールだ。また、新商品を購入した顧客には、使い心地や意見を尋ねるフォローコールを行う。最後が、商品がきちんと届いているかを確認するコールである。
現在、B to Cの顧客は10万人。うち、4万人を数えるアクティブな顧客がアウトバウンドの対象となっている。ホテル・旅館などの売店で同社製品を購入し、同梱のアンケート、「ご意見書」を返信してきた顧客にもアウトバウンドを展開する。
「ご意見書」は月600通に達するが、返信してくれた顧客は言わばホテル・旅館の顧客であり、同社との直接的な接点はない。このため、いきなり電話をかけるのではなく、まずは礼状やDMを送付するなどして、「電話がかかってくるかもしれないという、雰囲気作りをすることが大切」と志水氏は言う。「ご意見書」はわざわざ書き込んで投函する労力が必要とされる。それにもかかわらずコンタクトしてくれた顧客に対して、「まずは筆でお返しすることがポイント。また、いきなり電話をすると驚かれるお客様もいる」(志水氏)。
業務スタート当初は、興味を示してくれた顧客に感謝の気持ちを伝えたいという思いがはやり、すぐに電話をかけたこともあったという。しかしその後、やはり電話をかける前にある程度の関係を構築し、そのあとで電話をかける2ステップ方式がベストとの結論に至っている。
また、オペレータが顧客の“姿”をきちんと把握した上で電話することも重要だという。そこで同社ではCTIを導入、顧客と電話がつながった段階で、オペレータ画面に顧客の購買履歴、クレーム履歴、同社側から行ったプロモーション履歴をポップアップし、第一声として「先日はお買い上げありがとうございました」「先日は配送が遅れ申し訳ありませんでした」などの個別対応ができる体制を整えている。
B to Bのコツは顧客の日常を知ること
B to Bの対応も、ほぼB to Cに準じている。観光シーズン前に、商品が切れていないか、新たに必要なものがないかを尋ねるのが基本だ。現在、法人顧客は7,000件となっているが、データベース化された旅館・ホテルの数は3万5,000件。まだ取り引きのない企業に対しては、積極的にアプローチをかけていきたい考えだ。法人向けアウトバウンドの難しさは、電話をかけた際に「いつもの商品を、いつもの所へ、いつものように届けてほしい」と言う顧客が多いことだ。ここで数量確認をするようでは、「何度言えばわかるの」というクレームにつながりかねない。B to C同様の顧客情報の中から「いかにお客様の日常を把握してトークを進めるかが肝心」(志水氏)なのだ。
オペレータを手厚くケア
テレリーブルでは基本的にインバウンド、アウトバウンドのオペレータを分けているが、適性を見て業務変更を行うこともある。
業務を変更する場合には、次のようなステップを踏んで、より難易度の高い業務へと移行していく。①Bto Cのアウトバウンド、②B to Bのアウトバウンド、③B to Cのインバウンド、④B to Bのインバウンド。志水氏によると、アウトバウンドはオペレータが相手に伝えるべき内容を事前に把握しているので応答しやすいが、インバウンドは話の展開が予測できないため、対応が難しいという。
また、アウトバウンドの中では御用聞きの難易度が最も高い。相手の声の調子を見極めなければならないからだ。ベテランのオペレータでも時として顔色が変わる事態も起こる。顧客とのやりとりにおいては、本来は顧客が言っていることを理解した上で「それでは、こういたしましょう」と提案することが大切なのだが、オペレータが萎縮してしまうとその肝心の解決策提示ができなくなってしまう。そうした場合には、SV(スーパーバイザー)がコールを引き取る。さらに、一度オペレータを席から離し、時間をおいてから業務に戻すよう配慮する。必要とあれば、SVがパーソナル・ミーティングを行い、萎縮したオペレータの気持ちが落ち着くよう、心理的なサポートも行う。

コールセンター内の様子
全体の30~40%の売り上げを目指す
アウトバウンドはDMと違い、レスポンス率が分かりにくく、売り上げの予想もしにくいのが問題と、代表取締役社長の志水徹男氏は指摘する。現在、アウトバウンドにおける売り上げは、B to C直販を行うリーブルの総売上高の15~20%だが、30~40%を目指したいという。同社では、顧客とのコミュニケーションはうまくいっているし、意見の収集、商品への反映も十分に行っていると認識している。そこで今後は、コミュニケーションを売り上げまで確実に結び付けていくことが目標。優良顧客・休眠顧客などといった顧客別の対応も可能となるよう、顧客データの分析ノウハウをさらに蓄積していきたいとしている。