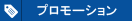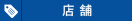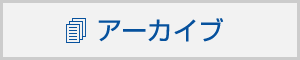各売り場担当者が得意客を手厚くケアする三越のお帳場制度は広く知られているが、お得意様営業部の発足により、得意客とのコミュニケーションはさらに強化された。現体制にたどり着くまでの模索と、得意客との関係作りに迫る。
稼働率低下の原因はニーズと提供する情報のミスマッチ
三越では越後屋時代から伝わる、得意客を各売り場担当者がOne to Oneでケアする「お帳場制度」をより活性化させるため、1998年に「お得意様営業部」を発足させた。当初15名でスタートした同部は現在300名体制にまで拡大し、得意客を特別に招く「特別招待会」の客単価は8万~9万円。3日間でおよそ10億円を売り上げるなど、著しい成果を上げている。現在、得意客だけが持つ「お帳場カード」の発行数は11万5,000枚。うち95%に当たる11万3,000名の得意客を同部が預かり、徹底したOne to Oneを実施している。それではまず、なぜ同部が発足するに至ったのか、その経緯から説明しよう。
お得意様営業部 ゼネラルマネジャー 黒部篤志氏によると、1998年当時は、担当者が顔を覚えていない得意客の数は全体の半数に達していた。これは社内調査の結果明らかになったもので、その理由としては、まず人材の流動化により顧客の引き継ぎがスムーズにいかなくなったことが挙げられた。また、少数精鋭を基本とする経営戦略により、ひとりの担当者が抱える顧客数が飛躍的に増加し、引き継ぎの際に顧客に挨拶ができない、また、顧客宅を訪問できないなどの状況が生まれていた。しかも顧客情報は各売り場担当者が保有するなど、社内のあちこちに分散していた。
そこでまず同部では、これまで売り場がケアしていた休眠顧客4,000~5,000名を預かり、スタッフ15名に対してエリアごとに顧客を振り分けて顧客訪問を実施。営業は一切抜きで顧客とのコミュニケーションを図り、顧客が三越に対してどのような気持ちを抱いているかをリサーチした。「担当者が挨拶に来たのは初めて」という声が出るなど、休眠顧客とは言え、One to Oneを重視してきたはずの同社にとっては「大変なショック」(黒部氏)だったという。「まずは顔を覚えてもらおう」。ひたすら顧客宅を訪問し、顧客と直接触れ合ううちに、2つの大きな発見があった。
ひとつは、顧客が望んでいる情報や商品と、同社が届けるそれとに大きなミスマッチが生まれていたこと。もうひとつは、「商品を自宅に持ってきてもらうよりも、実際に売り場に足を運び、より多くの商品の中から好みのものを見つけたい」という要望が多数を占めたことである。商品情報があふれ、交通の便が発達した現代社会においては、まず来店を促進し、多くの商品の中からセレクトするための手助けが大切であることを痛感した同部は、徹底した関係作りによる来店促進を業務目標に掲げた。そして、顧客の要望が明確になってきた1998年夏に、服飾雑貨部の得意客およそ4,500名を対象に、本格的な活動をスタートさせたのである。
特別な要望がない限り、顧客宅を訪問する際に商品を持参することは「原則禁止」(黒部氏)。「せっかく来てくれたのだから何か購入しなければ」と感じがちな顧客のプレッシャーやストレスを取り除き、この担当者とは付き合っても大丈夫という安心感を感じてもらうことで信頼関係を築いていった。同部発足からおよそ1年間を、とにかく顧客の元へ足を運び、帰社したらお礼の電話、その後にサンクスレターを送付するなどのコミュニケーション作りに費やしたのである。

年11回発行の「お帳場通信」(左)。限定販売会や旅行に加え、一般の催しも同時に案内される(右)
予想をはるかに上回る得意客が来店
こうした中、お得意様営業部は1999年に120名体制へ移行し、各スタッフが200~400名の得意客を担当することとなった。この段階では、3つの改革が行われた。ひとつは、「担当顧客は自分の顧客ではなく三越の顧客」という意識改革の徹底である。同社の顧客を担当者が「お預かりする」という意識を浸透させた。次に、チーム制の導入である。まず顧客ひとりに対し正担当者1名を決め、それをサポートするアシスタント2名を配置する。来店時に担当者が不在の場合にはアシスタントが対応、それもできない場合にはマネジャーが対応し、いつ得意客が来店しても顔見知りのスタッフがいるという体制を築いた。
情報提供を主とした顧客訪問、電話、はがき、来店時の手厚い対応により、顧客の気持ちは徐々に変化。それに伴い、来店頻度が高まっていった。当初、得意客専用に設置されたサロンの利用者数の目標は平日100名、土日150名だったが、実際にサロンを訪れた得意客数は平日200名、土日300名と予想を大きく上回った。さらに現在では、平日400名、土日600名に上っている。
コミュニケーション法は顧客宅訪問、はがき、電話
それではここで、現在300名体制にまで拡大した同部のコミュニケーション法について紹介しよう。同部の業務目標は得意客の来店促進にあるので、自宅訪問などによる関係作りや、月に13~15回開催されるイベント、および毎月開催の得意客のみを招待する特別招待会(1回当たり3日間開催)への案内が大切な役割となる。来場した得意客は必ず担当者が案内するが、担当顧客が来場しない場合でも、全スタッフに原則としてすべてのイベントに出席することが義務付けられている。
イベントについては、売上目標から何名の動員を図ればいいかを逆算して、スタッフひとり当たり何名の得意客を招致するかを決定する。これまでに蓄積したデータから、イベントの内容によって客単価を予測することが可能なので、イベントの企画段階で、何名の動員が必要かの提案も行うことができるという。その一方で、「おもてなし」をするための環境が悪化しないよう、想定人数を大幅に超えるような動員は行わない。ただし特別招待会は別で、得意客全員に案内し、現在、3日間行われる同会の平均来場者数は1万2,000名、客単価は8万~9万円で、3日間で平均10億~11億円を売り上げるという。
イベント案内は、はがきと電話で行う。一般のイベントの場合には手書きのはがき、特別招待会は印刷したはがきをまず送付するが、これには企画趣旨などが説明されているだけで商品の説明はほとんどない。しかも送付するのは、このはがき1枚だけだ。ではどうやってイベントの詳細を顧客に伝えるのか。それは電話である。一般のイベントの場合には、規模にもよるがスタッフひとり当たりおよそ20~30件、特別招待会の場合は全得意客に対して電話をかけ、イベントの詳細を直接、個別に案内するのである。来場客には一人ひとりに対して、内容の異なる手書きのサンクスレターを送付する。また、年賀状も手書きが義務付けられているという。
これだけ多くのイベントに対する来場を促すためには、普段からいかに密接な関係を築き、顧客のニーズを把握した上で適切な情報を適切なかたちで伝えるかがカギとなる。だからこそ、同部ではイベント動員にどれだけ貢献したかで、スタッフの評価を行っているのだ。
コール状況も把握 顧客情報システムが始動
顧客情報は、2003年3月に稼動を開始した顧客情報管理システム「LTASS(エルタス/Life Time Adviser Supporting System)」で管理されている。それまで手書きで蓄積されていた顧客情報を、2002年に一気にデータ化。現在では、顧客の購入履歴・趣味趣向・来店状況・イベントへの来場状況や、スタッフの会議記録・営業記録、電話がつながった件数などの行動記録を、すべてLTASSで管理している。マネジャーはチームが担当している全顧客の、一般スタッフは担当顧客のデータを閲覧できるようになっており、必要な情報が常時アウトプットできる。
LTASSの稼動と同時に、同部では15名体制のコミュニケーションセンター(Cセンター)を発足させた。同部が預かる11万3,000名の顧客のうち、担当者が完全なOne to Oneを必要としないと判断した顧客や、そうした対応を望まない顧客など、約3万名をCセンターが担当し、特別招待会の案内などを電話で行っている。
持続的な成長のカギは新規顧客の獲得と全社的対応
お得意様営業部の成果はめざましい。得意客の売り上げは口座ベースで計算されるが、この数字は1998年以降3年間、年率10%の割合で増加。2002年度は日本橋本店のみで400億円、全国で580億円に達した。しかし現在は正念場を迎えており、昨年上期より売り上げの伸びが前年同期比6%程度にまで低下しているという。ただ、今年6月には上昇傾向に転じており、黒部氏は「こうした数字には現金による購入や他社クレジットカードによる購入が含まれていないため、実質ベースで考えると依然として堅調な伸びと考えられる」と話している。
それでは、同部の今後の課題は何だろうか。それは、いかに新規顧客を開拓するか、そして得意客対応をいかに全社へ拡大するかである。これまで同部は既存顧客の活性化に注力してきたため、新規顧客の開拓はほとんど行っていなかった。「既存のお得意様については数年かけて、今後どのようなお付き合いができるかを見極めてきた。既存のお客様で手一杯の状態で新しいお客様を開拓すると、拙速な見極めから大切なお客様を逃してしまう可能性があった」と黒部氏は振り返る。しかしお帳場カードは2年間購入がないと取り引きが停止されるため、売り上げを確保するには新規顧客の獲得も極めて重要な課題だ。
そこで同部では、Cセンターに顧客を割り振ったのを機に、新規顧客の開拓に取り組み始めた。方法は2つあり、まずひとつ目は、顧客による友人の紹介である。関係が深まるにつれ、「友人を紹介したい」との声が頻繁に聞かれるようになり、被紹介者が顧客と一緒に来店する機会をとらえ担当者が挨拶。交流をスタートさせている。もうひとつは顧客の家族を紹介してもらう方法で、家族ぐるみの付き合いを深めていくパターンである。
こうした取り組みは始まったばかりだが、すでに月200名のペースで新規の得意客を獲得している。
一方、これまで同部だけで行っていた得意客対応を、全社的な活動に拡大しようとする試みも始まっている。同部で「この顧客はこのブランドが好き」と把握していても、売り場の協力がないと、新商品が入荷した際に素早く得意客に情報を伝達するなどのケアはできない。そこで同部では、今年上期より試験的にゴルフ用品を販売するプロギア(PRGE)の売り場と連携。売り場担当者に得意客の顔を覚えてもらい、来店した際には同部担当者とともに商品選びをサポートするなどの試みを始めている。下期には美術など、より広範な部門にこうした取り組みを拡大したい考えだ。
小売業では、いかに多くの商品を販売するかの営業力を問うのは当然のことと考えられており、営業担当者の評価も売り上げベースで行われることが多い。これは利益を追求する企業活動において当然のことだが、同社ではあえてイベントの来場促進=顧客との関係性強化を中心とした得意客対応に切り替え、顧客の信頼を勝ち取ってきた。「売り上げは結果にすぎない」と黒部氏は言う。8月1日には担当者を再考するなどして新体制を敷き、得意客のさらなる獲得と、より密接な関係作りを目指す。