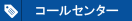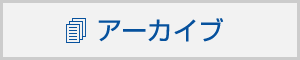77年の歴史を持つ中外製薬 (株) は2002年10月、F・ホフマン・ラ・ロシュ社とのアライアンスにより統合、新たなスタートを切った。 新生・中外製薬のミッション・ステートメントは、「革新的な医薬品とサービスの提供を通じて新しい価値を創造し、世界の医療と人々の健康に貢献する」 こと。 これに基づき運営されている、医療関係者および患者を対象としたコールセンターについて話を聞いた。
コールセンターも新たにスタート
2002年10月1日、世界有数のヘルスケアカンパニーであるF・ホフマン・ラ・ロシュ社との統合により生まれ変わった中外製薬(株)。 「革新的な医薬品とサービスの提供を通じて新しい価値を創造し、世界の医療と人々の健康に貢献する」ことをミッション・ステートメントに掲げ、ロシュ・グループの最重要メンバーとして、国内外において革新的な新薬を継続的に提供する、日本のトップ製薬企業となることを目指している。
同社がコールセンターを開設したのは、統合前の1995年1月。この年の7月よりPL法が施行されるのを受けて、顧客対応の強化を図ろうと東京本社内に開設した。応対スタッフには3名の社員を起用。小規模な受付体制でのスタートとなった。
同社では、従来より全国の支店内にドラッグ・インフォメーション(DI)を設けて、医師や薬剤師からの問い合わせを受け付けていたが、コールセンター開設後もDIに問い合わせが寄せられることが多くあった。これは複数の顧客窓口を持つ企業に共通することだが、それぞれの窓口から発信する情報を統一し、さらにその品質を一定に保つことは難しい。しかし、医療用医薬品という生命にかかわる商品を取り扱う同社にとって、均一な情報発信は不可欠である。そこで1999年10月、各支店のDIをコールセンターに統合。DI担当者を本社に呼び寄せ、人員の拡大を図った。
さらに今回のロシュ社との統合を機に、コールセンターの受付体制を一新。ロシュ社の顧客対応人員を加え、新たなスタートを切った。現在、医薬情報センター製品相談グループが運営・管理を担っている。
十分な情報提供の実現に向けてマルチチャネル化
コールセンターの業務内容は、次の2つ。まずひとつ目が、問い合わせ受付業務。医師・薬剤師・看護師・卸といった医療関係者、および患者やその家族といった一般消費者からの問い合わせに対応している。2つ目が、ヘルプデスク業務。MRと呼ばれる同社営業担当者のサポートを目的に、外出先からの問い合わせに対応している。
受付窓口には、電話、FAX、ホームページを活用。電話とFAXにはNTTコミュニケーションズのフリーダイヤル・サービスを採用している。
マルチチャネル化の理由は、顧客サービスと適正使用の推進にある。医薬品というものは、使用法が分からなければ効果が得られなかったり、逆に毒物になってしまう可能性がある。つまり、物質に情報が加わってはじめて医薬品となるのだ。商品には必ず使用法などを記した文書が添付されているが、それはその商品を使用する際に必要な最低限の情報に過ぎない。そのため、十分な情報を提供できる環境を整えるためにも、マルチチャネル化は不可欠であった。
加えて、お客様の声の集約化を推進する目的もある。中でもフリーダイヤルは、遠方のお客様が通話料を気にせず、電話をかけられる環境作りに大きく貢献している。
コールセンターでは、営業担当者からの問い合わせが重なってフリーダイヤル回線をふさいでしまい、お客様に迷惑をかけることのないよう、営業担当者からの問い合わせには専用の一般加入回線を設けている。
現在、コールセンターの告知媒体には、主に製品に添付している説明書や営業担当者が配布する説明書を活用。このほか、卸業者が独自に作成する製薬メーカーの問い合わせ窓口一覧表や医学薬学専門雑誌でも告知を行っている。
システム構築のポイントは“データベース”と“フィードバックの仕組み”
現在、コールセンターのスタッフ数は21名。このうちマネージャー1名を除いた20名で、10名ずつの2チームを編成。それぞれにチームリーダー1名を配置している。受付時間帯は午前9時から午後5時30分まで。前述の2チームが午前と午後の二交代で対応に当たっている。受付時間外は、営業時間をアナウンスすると同時に、緊急用電話番号を案内。副作用対応などには24時間365 日対応可能な体制を敷いている。
コールセンター・システムには、CTIを導入。NECネクサソリューションズのiVew工房をカスタマイズして使用している。カスタマイズには約1年を要した。というのも、iVew工房の導入を決めてから半年後に稼動させたが、その後ロシュ社との統合が決まり、製品数、ブース数の増加に伴い、再度カスタマイズが必要になったためである。再カスタマイズに当たっては、ロシュ社で使用して い た シ ス テ ム ( Lotus Notes/Domino)の利点を活かした。
カスタマイズの際、重視したポイントは2つある。ひとつはデータベースだ。顧客情報、製品情報、問い合わせ履歴のほか、文献情報、FAQといった膨大なナレッジデータから必要な情報を短時間で探し当てるには、まず、データベースが整備されていなければならない。もうひとつは、営業担当者へのフィードバックの仕組み。営業担当者は、全国の医療施設を定期的に訪問している。その病院から問い合わせがあった場合、誰からどのような問い合わせがあり、どう回答したのかを逐一知らせておけば、営業担当者が訪問先でフォローすることが可能となり、より好ましい関係を構築できるというわけだ。
システム構築には大変な苦労があった。既存のCTIシステムは、一般消費者向けの商品やサービスを扱う業務を想定したものが多く、それを医療用医薬品のB to B顧客対応業務に落とし込む作業に、最も労力を割いたという。
ワン・ストップでの回答率向上に努める
問い合わせ内容を見ると、医療関係者および営業担当者からは、製品や医学に関する質問が中心で、副作用、薬剤の使用法、効能効果に関する問い合わせが多く寄せられる。一方、一般消費者からは病気に関する悩みを相談されることも多いという。
これは統合前の数字になるが、受付状況を見ると、2001年には年間2万件の問い合わせが寄せられた。このうち電話が75%、支店などからの転送が20%。FAXとeメールは合わせて5%とごくわずか。インターネット利用者が増加しているといはいうものの、まだまだ医療関係者との日中のコミュニケーション・メディアの中心は電話だと言えよう。
もうひとつ注目したい数字がある。それは20%に及ぶ「支店などからの転送」だ。転送はお客様を待たせてしまうほか、操作ミスで電話が切れてしまう可能性もある。今後、コールセンターでは、フリーダイヤル番号の周知に努め、ワン・ストップ・ショッピングならぬ、ワン・ストップでの回答率を高めていきたいとしている。 具体的な施策としては、支店などに問い合わせてきたお客様に対して、その都度フリーダイヤル番号を案内し、1件1件地道に知らせていくほか、各種資材や営業担当者の名刺への記載、コールセンターのパンフレット作成などを検討しているという。
続いて、受付状況を利用者別に見ると、総コール数の50%は営業担当者となっている。200床を超える大規模な病院へは、頻繁に営業担当者が訪問しており、その際に直接、質問を受けることが多いためだ。お客様からの問い合わせは、病院薬剤師が20%、調剤薬局の薬剤師が12%、卸業者が10%、医師が5%、患者など一般消費者が3%となっている。
統合後は、製品数が増えたため、問い合わせ件数が2倍弱に増加。コールセンターでは、年間受付件数も2倍に増加するものと予測している。
こうした数字を踏まえ、同センターでは今後1 年をかけて、電話では得られない視聴覚的情報コンテンツを持ったFAQ ポータルを構築、電話の利便性に引けを取らないセルフサービス機能を備えた、“Web 問い合わせ窓口”を開発する意向だ。

本社内にあるお客様相談室の様子
ヒューマンリソースの効果的活用が課題
コールセンターの一次回答率は95%と非常に高い。その理由は、薬剤師あるいは薬物に関する豊富な知識を持った人材を起用していることにある。残りの5%は、大半が、注文や企業の政策に関する質問といった、コールセンターの業務外の用件である。
ところが、実際に寄せられる問い合わせは、専門性の高いものばかりではなく、製品の発売日や製品識別コードに関する問い合わせなど多岐にわたり、その難易度もさまざま。製品情報データベースが構築されていれば薬剤師でなくても回答できる問い合わせも多くあり、コールセンターでは、すべてに専門知識を持ったスタッフが対応するのが果たして最も良い方法なのかという疑問を持っている。しかし、医療用医薬品に関する問い合わせ受付には、高い専門知識が必要とされるため、テレマーケティング・エージェンシーなどへのアウトソーシングが難しく、同社に限らず医療医薬品メーカーのコールセンターでは社員が対応に当たっているのが現状だ。
ヒューマンリソースの効果的な活用を目指すコールセンターでは、この課題の解決策を見出そうと、2002年10月より外部スタッフを1名採用し、テスト・オペレーションを開始。アウトソーシングの検討をはじめた。コールセンター内での回答率の維持と質の向上を目指して、ヒューマンリソースを最大限に活用し、顧客満足を得られる運営体制を模索しているところだ。
具体例を挙げると、コールセンターで取り組んでいる課題の難しさがよく解る。例えば、副作用に関する問い合わせの場合、「この薬を飲んだら下痢になりました。そういう副作用はあるのでしょうか?」という質問には、データベースを見て副作用の有無を回答することができる。しかし、その場合どうしたらいいのかという質問になると、専門知識が必要になる。対処法は、患者の病態などによって異なるため、マニュアル化しにくいのが実際のところ。一般的な内容と専門的な内容が入り交じった質問にスピーディーに対応できる仕組み作りがポイントだ。
顧客満足は“知識”と“スキル”から生まれる
コールセンターに求められるものは、スピードと情報の質の2つ。同センターでは、今後はより一層、研修を強化する必要があると考えている。従来は、月に1度、チームごとに学術知識に関する研修を実施。また、お客様に正しい情報を提供するために不可欠な、他社製品の知識を身に付けることにも注力していた。加えて、応対スタッフが事例に基づいてFAQを作成することも、非常に効果的な研修になっていたという。
そして忘れてはならないのが、電話応対に不可欠な応対スキルの研修だ。極端な言い方をすれば、お客様からの問い合わせが、有意義なコミュニケーションになるかクレームになるかは、応対スキル次第。知識とスキルが相まって、はじめて顧客の満足を得られるのである。今後同センターでは、定期的に外部講師を招くなどして、少人数での集合研修を実施していく考え。 また将来的には、モニタリング機能を導入して、実際のオペレーションに即した教育を行うことも検討している。同センターでは、モニタリングは応対スキルを磨く有効な手段であると認識しており、積極的に活用していく意向だ。
また、病気について問い合わせてくる患者やその家族への対応には、カウンセリング的な要素も必要。製品知識だけで対応していると事務的になりがちなため、患者の気持ちを理解することにも努めていきたいとしている。
“感度”と“鮮度”が情報を活かす
コールセンターでは、収集した声を活かすために、情報のフィードバックの仕組みを整えている。
まずはじめに、各営業担当者へのフィードバックが挙げられる。お客様から寄せられた問い合わせとそれへの回答内容は、営業担当者が携帯しているモバイル端末にeメールで連絡。営業担当者の対応が必要な場合は、スピーディーにアクションが起こせる体制を実現している。
次に挙げられるのは、本社内の関連部署へのフィードバック。月に1度、問い合わせ履歴の一覧表を作成し、提出している。微妙なニュアンスまで伝わるよう、一覧表作成の際には、生の声をそのまま伝えることに留意しているという。加えて、4半期ごとに副作用、品質、包装といった項目を決め、 項目ごとに集計し、レポートを作成している。
さらに必要に応じて、提供すべき情報が徹底されていないなど対処すべき事柄をピックアップし、関連部署にフィードバック。改善を促している。
顧客満足度の向上、営業サポートに加えて、危機管理も同センターの大きな役割のひとつ。お客様の声から危機を察知するためには、情報の鮮度と読み取る感度がポイントと言える。対処が必要な事柄の洗い出しには、テキストマイニング・ツールを活用しているが、より一層、フレッシュな情報をキャッチできるよう、効果的に活用していく意向。加えて、 お客様の声を聞くだけでなく、積極的に質問を投げかけることにより、情報収集に注力していきたいとしている。
さらに同センターでは、関連部署へのデイリーなフィードバックが必要ではないかと考えている。複数の立場の異なる視点から見ることにより、新たな事象が見えてくる可能性があるからだ。
コールセンターが目指す“革新的なサービス”とは
冒頭で述べた通り、新生・中外製薬のミッション・ステートメントは「革新的な医薬品とサービスの提供を通じて新しい価値を創造し、世界の医療と人々の健康に貢献する」こと。ここに掲げられている“革新的なサービス”を提供する一翼を担うのがコールセンターである。革新的なサービスとは何かを突き詰めて考えると、お客様がこれは革新的だと思う“スピード”と“クオリティ”を作り出していくことと言える。同センターでは、インハウスとアウトソーシング、システムによる対応とパーソナルな対応といったさまざまな組み合わせを研究していくと同時に、既存のシステムやヒューマンリソースを活かしながら、スピードとクオリティを革新する、そんなコールセンターを目指していきたいとしている。
統合に伴い、中外製薬にロシュの持つグローバルなバックボーンが加わった。コールセンター先進国である米国やヨーロッパのノウハウ、そして世界各国に製品を販売しているからこそ得られる海外の業界情報などの資源を最大限に活用する仕組みを作ることもまた、“革新的なサービス”につながると考えている。