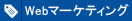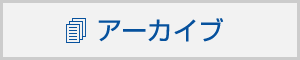コミュニティサイトの活用が大きな売り上げにつながったにもかかわらず、サイト上では売り上げではなくブランド形成を重視することを決定した東洋水産。成功が生んだ意外な「疑問」が、この結論を導き出していた。
120万食を売ったインドメン
カップ麺や冷凍食品の「マルちゃん」ブランドでお馴染みの大手加工食品メーカー、東洋水産(株)。コミュニティサイトを活用して集めた顧客のアイデアを商品化した「インドメン」が大成功を収め、120万食を完売したのは2000年3月のことだ。しかしその後、第2弾企画は出ていない。広報宣伝部 課長の角忠氏は「コミュニティサイト“マルちゃん学園”を含むインターネット活用は、売上高ではなく、ブランド力の向上を第一義に掲げていきたい。そのためには、記号化されたブランドの背後にある活動・志向・思想などを開示することが重要となる。今後、マルちゃん学園を含むインターネット活用は、企業ブランドからプロダクトブランド・レベルまでのすべてを考慮した上で、あらゆるステークホルダーの要請および要求に対応することを目指す」と語る。
マルちゃん学園の2002年の月平均トップページビューは20万。キャンペーン時には月当たり40万ページビューに達している。コンテンツはおなかのすき具合をチェックする「実験室」、製品情報を案内する「博物館」、通信販売機能の「売店」、テーマごとに顧客の意見を収集する「クラブ活動」など、名称変更や内容の更新はあるものの、2001年と比べて大きな変化はない。コミュニティサイト活用により大きな売り上げを確保した同社が、なぜECや商品開発を主要な目的としたサイト作りに傾かなかったのだろうか。
その理由を探る前に、まずインドメンについて復習しておこう。同商品は、現在も同社が協賛しているMBK流通パートナーズ主催の「Food’s Foo」がカップ麺のアイデアを募集。応募総数1,051件の中から人気投票を行い、トップに輝いた「とろっとおいしいカレーラーメン」を東洋水産が商品化したものだ。120万食を完売する快挙もさることながら、「ネットを活用した顧客との双方向コミュニケーションによって誕生した商品」として、メディアでも採り上げられ話題となった。
企画進行中に「なぜ?」の思い 成功を疑う2つの理由
しかし、マスコミを通じて周囲が盛り上がりを見せる一方で、「顧客とのコミュニケーションを抜本的に見直さざるを得ないような戸惑いがあった」と角氏は当時を振り返る。
悩みは大きく分けて2つあった。ひとつは、インドメンがなぜ爆発的に売れたかの理由を確定できなかった点だ。当時、コミュニティサイトを活用して顧客の声を集め、それを商品化する企画は新鮮だったが故にマスコミの注目を集め、NHKやフジテレビの報道番組や新聞・雑誌で採り上げられるなどした。このため、同商品が売れたのは「顧客が同社の製品に感動や共感を感じたから」、もっと言えば「同社に対するファンが増えたから」という要因以上に、マスメディアによるPR効果が大きかったためではないかとの疑問が生まれてきた。
2つ目は、インドメンの成功が、双方向型コミュニケーションの成功というよりも、話題性喚起というプロモーションとしての成功の色彩が強かったのではないか、という疑問である。アイデアの投稿や人気投票など、同企画の参加者は3万人に上ったが、これら顧客との関係はコンテスト形式の企画が終了した時点で途切れてしまった。また、顧客とのディスカッションを通して商品を開発したのではなく、絞り込んだひとつのアイデアを商品化したにとどまっていた点も、こうした疑問につながっていったという。同じ企画を2回繰り返した時に成功するかどうかは、不確かだったのだ。
さらに、同企画ではマルちゃん学園および東洋水産ホームページとの関係性が明確でなかったために、顧客に同社のブランド体系を認知・理解させにくい側面があったようだ。
「マルちゃんブランドの認知度はかなり高いが、東洋水産そのものの認知度は満足とは言えない。まず東洋水産というコーポレートブランドがあり、その下に商品群を束ねたマルちゃんブランド、さらにその下に赤いきつね、緑のたぬきなどのプロダクト・ブランドが並んでいる。シナジー的に、各階層のブランド価値の向上を実行することは非常に難しい」(角氏)。例えば、赤いきつねを知っていても、それをマルちゃんブランドと認識していない顧客もいるし、同ブランドからすぐに東洋水産をイメージできる顧客も少ないと思われる。
同社ではインドメンのような企画も、ブランド全体の価値向上に引き上げなければ、顧客とのコミュニケーションが成功したとは言えないと考えているのだ。
今後、目指すはブランド重視のサイト運営
それでは今後、同社のコミュニティサイトはどこへ向かうのだろうか。ひとつ、明確な目標がある。それは、すべての階層のブランドに関する情報を顧客に向けて発信・提供するとともに、それに対する顧客情報をフィードバックすることである。同社では、東洋水産の活動、そして思想をありのままの姿でネット上に投影したいと考えている。東洋水産とマルちゃん学園のネット上の位置付けも、事業戦略なども視野に入れて再検討していく。また、細かなところでは、サイト上にプロダクトごとのコンテンツを開設し、製品とマルちゃんブランドの関係をより強く感じてもらうとともに、各製品の“ファン”心理に合ったコンテンツを用意することで、ロイヤルティをさらに向上させたいとしている。
さらに今回の取材では、同社が理想とするコミュニケーションの姿も明らかになった。
角氏は「双方向のコミュニケーションで重要なのは、まずこちら側が企業としての姿勢を示すこと」と指摘し、その理由を「消費者を取り巻く情報環境を考えた場合、“待ち”の姿勢では埋没してしてしまうため」と説明。さらに、「メーカーは顧客とのコミュニケーションの第一歩として、まず商品を通して顧客に語りかけなければならない」と言い切った。もちろん、顧客から意見を聞くことは大切だ。しかし、声にならない潜在ニーズを汲み取ることにメーカーとしての真骨頂があることもまた事実だ。顕在化したニーズはすべての企業にとって明らかなニーズであるため、競争優位に立てないからだ。ソニーのウォークマンを例にとれば分かりやすいだろう。ウォークマンが登場するまで、顧客に街中を歩きながら音楽を聞くという発想はなかった。メーカーの持つ豊かな創造力が顧客の心をとらえ、ブランド力につながったのである。
また、商品が誕生するまでの物語を知っている人間が、その商品の世界観を表現するためにネットその他の顧客接点を通して顧客とコミュニケーションを図ることも、理想形のひとつと言う。商品開発の現場と情報発信の現場を一本の糸で結べば、一貫性のあるより強固なブランドイメージを生み出すことが可能となる。組織変革や意識改革が必要となるなど実現は至難の業だが、角氏が宣伝担当者としてコミュニケーション活動の業務に携わる一方、週に半分は商品開発に携わるなど、具体的な試みがすでに始まっている。
企業が打ち出す明確なビジョンのもとにブランド力を向上し、ファンとなった顧客が企業と対話するための “ 場”を提供する。その場のひとつが、コミュニティサイトであるはず――同社ではこのような指針を掲げた上で、マス媒体、ネット活用を含めてもう一度、顧客とのコミュニケーションのあるべき姿を再検討し、有効なコミュニティサイトの活用法を探っていく意向である。