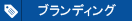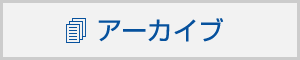新ブランド浸透をめざす
日興コーディアルグループでは、3年前から独自に顧客満足度や認知度を測る調査を実施してきた。昨年からはカード会社、銀行、保険会社など異業種を含めた調査を開始している。最近の例では昨年11月に調査を実施、すでに集計結果が出て課題の洗い直しを行っている最中という。生保、損保といった明確な住み分けが崩れ、相互乗り入れが進む状況において、顧客が投資信託や保険を選ぶ際に、競争相手が同業他社とは限らない。「調査の結果を顧客とのコミュニケーションだけでなく、ビジネスモデルの段階までどう落とし込んでいくのかが問題」と同社ブランドマネジメント部副部長の清水敏也氏は言う。
証券大手・日興證券グループが持ち株会社体制へ移行し、日興コーディアルグループとして新しいスタートを切ったのは2001年10月1日のことだ。これに伴い、旧日興證券(株)で行っていた全証券業務を引き継ぐ「日興コーディアル証券(株)」も発足した。
合併したわけでも外資と資本提携を結んだわけでもない同社が、なぜ社名変更に及んだのか、また、社名の変更が日興ブランドにどのような影響を与えたのかを追った。
ブランドマネジメント部を発足
旧日興證券グループが持ち株会社の立ち上げを計画したのは、数年前にさかのぼる。当時はまだ法制度が未整備だったため、タイミングが昨年にずれ込んだ。この間、金融ビッグバンが進み、従来の横並び的な方法ではじり貧になるのは免れないとの危機感が経営陣の中に生まれた。
そんな中、2000年にブランドマネジメント室を発足。2001年3月末の組織改変に合わせるかたちで、ブランド推進課とWeb推進課を統括する総勢17名のブランドマネジメント部へと昇格した。ブランド推進課は従来のブランド構築を担当し、Web推進課がEブランディングを担う。
ブランドマネジメント部の役割は、「社内でも理解してもらうことが難しい」(清水氏)が、ブランド戦略を含む経営理念の浸透を社内に周知徹底したり、各支店の広報活動に対しアドバイスを行うなど、その活動は多岐にわたる。
「これがブランディングだと言うつもりは毛頭ない」と前置きした上で清水氏が語る社名変更にまつわるブランドへのこだわりをまとめると、次のようになる。
「ブランド」を構成する要素は大きく分けて4つ。「認知度」「自分にふさわしいかどうか」「そのブランドに対してあこがれが持てるかどうか」、そして「差別化」だ。ところが、長く護送船団方式に守られてきた金融業界は同質のサービスに偏りがちで、顧客側から見た比較材料が乏しい。認知度においては100%近い抜群の成績を収める企業でも、ほかに抜きん出る差別化要因を持っておらず、この没個性が日本金融界最大の弱点となっている。
もちろん、財務的な手法によって決算から算出される適性株価水準を上げ、キャッシュフローを増やして企業力をアピールすることはできる。しかし、これでは世の中の眼が有形固定資産から無形資産へ、ハードからソフトへ大きくシフトする中でブランド力を高めていくことはできない。
では、何をしたら良いのか。
「差別化を図っていく」という新しい経営理念の下、厳しい競争を断固とした姿勢で戦い抜き、「本当に顧客本位の、末永くお付き合いいただける金融機関を目指す」という経営陣の強いメッセージを目に見える形で伝えるため、グループ会社名に「コーディアル」(CORDIAL)を付与した。「誠心誠意の、真心を込めた」という本来の意味に、「CORD/きずな」と「DIALogue/対話」といった独自の解釈を加えている。
証券業務を引き継ぐ旧日興證券については、「あえて社名変更をする必要はない」との見方もあったが、強行突破を図った。その理由について、清水氏は次のように説明する。
「まず、日興コーディアルグループと日興コーディアル証券は一体であることを見せたかった。もうひとつは、証券業務を通じてのさまざまなやり取りの中で、実際に顧客と触れ合うフロント業務の担当者にコーディアルが意味するところ、誠心誠意と真心を常に意識してほしいとの願いがあった」
電話対応で社名を名乗るたび、また、顧客から新しい社名の意味を尋ねられるたび、社員自身がコーディアルの理念を再確認することを狙った。
新しい社名に対する社内からの反発は「想定以上」(清水氏)だったが、そこまでやるのだという経営陣の覚悟を伝えたという。顧客からの評価は、女性には好評、50歳以下の男性にも受けが良かった。しかし、旧日興證券と何十年も取り引きをしてきた50歳以上の顧客からは「外資系になったのか」といった疑問の声も聞かれ、営業担当者が丁寧に説明して回り、理解を求めたという。
意思統一をどう図るかが課題
社名変更に伴う社内の摩擦。それを収めることができたのは、コミュニケーション・キャラクターに起用されたイチロー選手の功績かもしれない、と清水氏は笑う。
一新された4つの経営理念、「コーディアル=きずなと対話」「革新と挑戦」「個性と自己実現」「社会人としての倫理観」とオーバーラップする実績を持つイチロー選手に、「コーディアルをかたちに」のメッセージを託した。金融商品と同様、曖昧で手に取って確かめることのできない理念を、野球の価値観そのものを変化させたイチロー選手の真摯な姿勢や考え方とシンクロさせることで、社員が自分のこととして受け止めるようになっていった。
「イチロー選手との会話を通して私自身が深く感動した。一般の人が期待する以上のものを彼は私たちに見せてくれる。この、期待を超えたところにあるもの、それがブランドなのではないだろうか。日興コーディアルと顧客とのきずなを築くとともに、社員とイチロー選手とのきずなも作っていく。そういった全体的な関連付けをいかに設計していくかがブランディングの醍醐味かもしれない。やはり、やっている人間が楽しまないと良いものは生まれない」(清水氏)
ブランディングにおいて最も難しく、各社が頭を悩ませているのは、実は社内の意思統一といえる。いくら経営陣が熱くなっても、社員に伝わらないものは顧客に伝わりようもない。セミナー等の開催だけでは浸透度に限界があり、イチロー選手効果の高い同社でも、この点については頭を悩ませている。