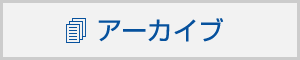顧客の要望に応えて通販を開始
(株)ふくやは 1948 年の創業。業務用食品などを販売する雑菓商としてスタートしたが、創業の翌年に先代社長が「味の明太子」を発案、製造を開始したのである。
以来同社は、地域に密着した事業展開を行ってきた。36 の店舗はすべて、福岡県内にある。例外的に羽田空港と浜松町のモノレール駅構内でも販売を行っているが、基本的に県外には出店しない方針を貫いている。“博多発”の情報を発信し続けたい、地元博多に利益を還元したいというのが、その理由だ。
福岡を訪れて辛子明太子のファンになった人たちから、「ぜひ送ってほしい」という要望が数多く寄せられる。そこで同社では、1970 年頃から、前払いの現金書留で代金を受け取り、商品を発送するサービスを実施してきた。1985年にはお客様の便宜を図り、電話で注文を受け付ける「受注センター」を開設。本格的に通信販売事業を開始して、現在に至っている。
年 4 回発行のカタログには、オリジナル商品の「味の明太子」「数の子めんたい」「いかめんたい」などのほか、ふぐちりセット、博多ラーメンなど約 90 品目の珍味が並ぶ。オリジナル商品はアイテム数では約 50%だが、売り上げでは約 85%を占めるという。カタログの仕様は 19.5cm×21cm、24 ページで、発行部数は夏・冬号がそれぞれ 60 万部、春・秋号がそれぞれ 5 万部。通販の実績客に郵送するほか、店頭でも配布している。通販の場合、客単価は約2万4,000円。レスポンス率は 23%に上るという。
新規顧客は、主に顧客の口コミで開拓されている。新聞、雑誌などへの広告展開は一切行っていない。その理由を、同社課長、横手了氏は「高い広告料をかけて獲得した新規顧客が、果たして固定化するかと考えると、はなはだ疑問。その点、顧客の紹介があった場合は、固定化率が高い」と語る。

ふくやの通信販売カタログと、料理ブック
お届けは注文の翌々日
顧客からの注文は、電話、FAX、申込専用の封書の 3 種類の方法で受け付けており、その比率は約 4: 3:3。特に届け先が複数にわたるギフトの注文では、申込専用の封書の比率が高くなる。
電話受付は月〜土曜日の午前 9 時から午後 5 時までで、日曜日と祝日の受け付けは行っていない。通常 50 名のスタッフが待機しており、ギフトシーズンには最高 100 名を配置する。
支払方法は、初回の注文だけは、代金引換か前払い。2 回目以降は郵便振替か銀行振込による後払い、代金引換のいずれかを選ぶことができる。初回購入を代引、あるいは前払いとしているのはトラブル防止のためだが、未収率は 0.05%と、実際には大きな問題にはなっていない。
商品配送にはクール配送を利用。正午までの受注分は、離島などの難配地区を除き、翌日のお届け。正午以降の注文でも、翌々日にはお客様の手元に届く。
品質に関する問い合わせやお客様のご要望などは、受注センターとは別に本社内に設置している「お客様サービス室」で受け付ける。男女合わせて 6 人のスタッフが、通信販売に限らず、同社の店舗や商品などについての幅広い問い合わせに応じる。この電話番号は、商品の包装紙などに記載、告知している。
さりげなく誠意を伝えたい
同社の通信販売を利用している顧客は、現在約 60 万人。地元福岡の居住者が中心だが、そのほかの地域にはほぼ人口分布通りに散らばっている。中心年齢層は 35 〜 50 歳だ。
同社では請求書を送付する際、新製品案内のリーフレットなどといっしょにアンケートハガキを同封している。このアンケートの回収率は約 8%だ。返信した顧客は、関連会社が製造したお菓子などを、必ずお礼として送っている。
そのほか、お客様に手書きのお礼状を送ることもあるし、商品の美味しい食べ方について問い合わせをしてきた顧客には、年 4 回作成しているオリジナルの料理ブックを送る。同社のきめ細かな顧客対応マニュアルにしたがって、個々の顧客のアクションに応じたサービスが提供されるわけだが、それもこれも、顧客には事前に告知されない。その意図を横手氏は、「お客様を驚かせたいんですよ」と説明する。
ちなみに同社では通信販売の利用実績によって、顧客を5段階に分けて管理している。以前は13カ月間、注文のない顧客はリストからはずしていた。しかし、「時代によって顧客の選別のしかたは変わる。スリーピング顧客を疎かにするのは得策ではない」(横手氏)。現在はさまざまなセグメントによって、スリーピング顧客を含めた顧客データベースの有効活用を図っているという。
同社の年商は約 175 億円。うち、通販の売り上げは約 72 億円だ。広告に頼らず、口コミを促進する地道な営業活動は、グルメブームや産直ブームに踊らされない緩やかな顧客増、売り上げ増を実現してきた。全国的に知名度の高い同社は、今後も“博多のふくや” であり続けるのだろう。