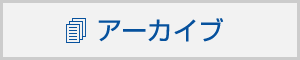■1970年代半ばに始まった消費者調査「Rage Study」の歴史
「Rage Study」はそもそも、1970年代後半と1980年代前半に、米国・ホワイトハウス内の消費者局からの委託事業として実施したもので、トラブルに直面した時の消費者行動を知ることを目的としていました。そしてこの調査結果から、“消費者の多くは苦情があってもトラブルとして申し立てず、結果的にロイヤルティは弱くなってしまうが、苦情を申し立てて解決した後は、ロイヤルティが高まる”という日本でもおなじみの「グッドマンの第一の法則」が生み出されるとともに、米国・ヨーロッパ・日本などにおける着信課金サービス(日本ではフリーダイヤル)の普及を促進することになりました。
その後20年間にわたり、この調査結果は多くの分野で活用されましたが、時間経過と共にデータが古くなってきたことから、「National Rage Study」として本調査を再開。以降、この20年間に10回にわたり実施しています。
そこで本日は、2023年に日米で同時実施した「National Rage Study」の一部を、両国の比較を交えてご紹介したいと思います。なお、日本における調査回答数は5,000件。以下では、実際の講演では「痛点」とされていた表現を、よりわかりやすく「トラブル」と記しております。

■2023年の「US-Japan Rage Study」の調査結果より
①トラブル体験後の消費者行動とロイヤルティの関係
まず、「購入した商品・サービスについて、過去1年以内にトラブルを体験した人の割合」では、「体験していない」が61%と米国の26%を大きく上回り、「体験した」は39%に過ぎませんでした。また、トラブルを体験した回答者のうち問い合わせをした回答者は49%に過ぎず、米国の79%を大きく下回っていました。しかし、クレームを申し立てない限りトラブルは解決しないわけですから、この事実はロイヤルティの低下を招くと共に、悪いクチコミを流布させることにも繋がっています。
また、日本の調査結果を「顧客損失モデル」に当てはめると、カスタマーサービスの応対に「満足」しているのは36%で、「どちらでもない」が21%、「不満」が22%、「適切な対応がなかった」が22%となっています。つまり、カスタマーサービスの対応に満足したのは1/3に過ぎず、2/3は満足していないわけで、企業に対するロイヤルティが損なわれていると言えます。これではカスタマーサービスに投じたコストは無駄になってしまいます。優れたサービスによる売り上げや好意的なクチコミへの貢献は、投下したコストの10~20倍にも達することから、消費者を満足させることが急務となっていると言えるでしょう。
②消費者が体験したトラブルの内容
ここでは最も高頻度なのは「不快な広告・宣伝」です。これは米国でも見られますが、消費者の不満の30%は、マーケティング・営業活動における透明性の欠如にあります。透明性は消費者を満足させる上で非常に重要な要素なのです。2点目に挙げられるのは、「品切れ」と「納品までの期間」です。これも日米に共通しており、特にコロナ禍の中でクローズアップされてきたと言えるでしょう。3点目に挙げられるのは商品の「品質」や「破損」です。これらのトラブルは製造工程にフィードバックして商品の改良などに役立てることが不可欠ですが、同時にこの手のトラブルを早く解決するためには応対スタッフがエンパワーされていることが必須となってきます。4点目として挙げられるのは「解約方法」です。消費者は簡単に解約できることを期待しており、この手続きが解りにくいとロイヤリティに悪影響が生じます。
体験頻度が高いこれらのトラブルに共通するのは、“消費者にとって不安に繋がる”ということですが、この“不安”は消費者の“不満”を生み出す重要な因子でもあります。加えて時間のロスにも繋がりますので、企業には品切れや納期に関する正確な情報を能動的に伝えることが求められます。これがなされていないと、消費者が自らの時間を使って、正確な情報を探索しなければならないわけです。
③トラブルを体験した時、消費者は何を思ったのか?
「トラブルが起きた際に被った損害」について4つの選択肢を挙げて回答を求めたところ、「時間を無駄にした」「精神的なストレスを受けた」が順に多く、「金銭的損害を受けた」「身体的傷害を負った」はさほど多くはありません。これは米国の調査結果にも共通しているのですが、多くの消費者はお金よりも時間を問題視しており、トラブルを速やかに解決できないことが、企業に不満を持つ要因になっていると言えるでしょう。
④トラブルを解決する際のコンタクトチャネルの比較
日本では「チャット」や「企業の公式SNSへの投稿」はそれぞれ13%、2%と米国に比べて低く止まっています。米国ではAIの進展に伴いチャットが躍進しており、日本の倍ぐらいの消費者が利用していると見られます。これはチャットの方が企業からの回答が早く得られるからであり、今後は日本でもチャットが伸びていくのではないでしょうか。また米国ではSNSの利用も増えています。米国の消費者は困ったり質問があったりする時に、SNSに積極的に投稿すると共に、企業からのレスポンスを期待する傾向にあるのです。
さらに(店舗などへの)「訪問」や「電話」についても、米国の数値は日本を大きく上回っています。この理由としては、米国ではコロナ禍が一服したことで店舗を訪れてマネージャーに回答を得ようと考える人が増加していることや、時差の関係もあって日本に比べてコールセンターの営業時間が長いことが挙げられるでしょう。
⑤カスタマーサービスにおける消費者の期待と実態のギャップ
日米両国を比較してみると、まず日本では米国よりも謝罪に重点が置かれており、「期待した対応」では米国の24%に対して日本は20%、「実際の対応」では米国の18%に対して日本は32%となっています。ここには日米の文化の違いが横たわっているものと思われますが、とは言え行動を伴わない謝罪は消費者の満足には繋がりません。我々は米国の企業に消費者への謝罪の重要性と合わせて、応対スタッフが柔軟性を発揮して問題解決に当たると共に、トラブルの原因を説明するように指導しています。日米を問わず、消費者はトラブルの原因を知ると共に、これが繰り返されないことを望んでいると言えるでしょう
この設問においてもうひとつ注目されるのは、「親身な対応」と「柔軟な対応」です。日本では、前者が24%、後者が19%と消費者の期待は高いのですが、実際の対応では前者が10%、後者が8%に止まっており、サービスの実態が伴っていません。この点については、米国では応対スタッフをエンパワーすると同時に、柔軟性を高めることに注力しています。例えば難しい局面でのアプローチについて予め4つの選択肢を用意しておき、スタッフに最適なアプローチを選ばせるといった方法も効果的です。こうした方法を採用することで、応対スタッフは画一的なアプローチから解放され、親身な対応も実現するのではないでしょうか。
⑥問い合わせを“しない”のはなぜか?
調査対象者に問い合わせをしない理由を尋ねたところ、「面倒だった」という回答が最も多くを占めました。したがって企業としては、消費者が気軽に苦情を申告できるように工夫すると同時に、彼らの気持ちを理解することが大切です。こうした中、米国では、“苦情や問い合わせは申告されない限り改善に繋がらない”旨のメッセージを訴求する企業も増えています。苦情率が増えることを懸念して、このような取り組みに尻込みしたくなるかもしれませんが、苦情に耳を傾けずに放置するのに比べて、10倍以上の売り上げが期待できるのですから、これに取り組まない手はないのです。
⑦クチコミの影響
自身が経験したトラブルについて何人に伝えたかを尋ねたところ、応対に「満足」した人では2人にポジティブなクチコミを伝えているのに対し、「どちらでもない」は-2.5人、「不満」は-3.3人、「適切な対応がなかった」は-3.3人、「コンタクトなし」は-2.2人という結果になりました。すなわち、トラブルがあっても苦情を申告しない人々からネガティブなクチコミが広がることが顧客全体のロイヤルティを下げ、セールスやマーケティングに悪影響を及ぼしていることは明らかなのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これらの調査結果から、カスタマーサービスにおいて、苦情を積極的に受け止めてトラブルを解消し、企業の透明性を高めること、エンパワーされたスタッフが柔軟性をもって消費者との感情的な絆を構築することの重要性は明らかです。こうした取り組みこそがカスタマーロイヤルティを高め、ポジティブなクチコミを拡散させて、企業に高い収益性をもたらすのです。つまりは、セールスやマーケティングに注力せずとも企業をリーダー的な存在に押し上げ、ビジネスに成功をもたらすと言えるでしょう。