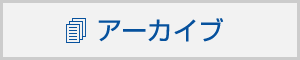2023年7月9日
本稿は、2023年3月31日に日本ダイレクトマーケティング学会が発行した学会誌『Direct Marketing Review vol.22』に掲載していただいた特別論文を、事務局のご厚意により公開させていただいたもの。章ごとに5分割して掲載しているため、「はじめに」「ダイレクトマーケティングの歩み」をまだお読みでない方は、そちらからご覧ください。
※【引用・参考文献】は➄の文末をご参照ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
前章では、ダイレクトマーケティングの歩みを簡単にまとめてみたが、私自身がこの世界に身を置いた40年超を振り返ると、その時々にさまざまなバズワードが誕生しては、いつしか消えていくことの繰り返しだった(図1)。そうした中、「以前にも同じような話を耳にしたことがある」と既視感を覚えることも少なくなかったが、果たして私たちは、過去の歴史に学ばずに同じことを繰り返しているのか、それとも企業環境の変化に適応して進化しているのか。以下に「D2C」「オムニチャネル/OMO」「サブスクリプション」という最近の3つのトレンドをピックアップして、私なりに考察を加えたい。
図1各キーワードのGoogle検索トレンド推移(2004年〜2022年)

➀メーカー通販 → D2C : 製造業の通信販売は新規事業開発から本業の活性化へ
まず1つ目のトレンドとして挙げるのは、B2C領域での「メーカー通販 → D2C」である。メーカー通販という表現は最近では耳にする機会が少ないが、1980年代に製造業による通信販売参入が活発化した頃には、この用語が広く用いられていた。当時、製造業各社が通信販売に参入したのは、エンドユーザーとの直接的なコミュニケーションを通して生活者ニーズを把握することが狙い。しかし、中間流通を通さずにエンドユーザーに直接、アプローチすることへの小売サイドからの反発も大きかったことから、既存商品とは異なる商品を通信販売したり、ディーラー経由で生活者にカタログや商品を提供することでリテイル・サポートに寄与したりする例が多かった。
私が知る限り、国内で早くからメーカー通販に乗り出したのはキリンビール・グループや明治乳業グループなど食品製造業であり、前者では1979年からビアマグ等の通信販売を開始、後者では1981年からマタニティ&ベビー&育児用品の通信販売を開始している。また、ディーラー経由での取り組みとしては、マツダ(株)が1982年から生活関連商品全般のカタログ販売を展開していた。これらのメーカー通販は、自社のブランド・イメージを生かして、キリンビールではビール、明治乳業では粉ミルク、マツダでは自動車といった主力製品の周辺領域における新規商品を通信販売する例が多かった。
その後、2000年代に入ってインターネットが人々の生活に浸透し始めると、化粧品や健康食品などのリピート商品を中心に、通信販売に参入する製造業が増加すると共に、本業周りのプロモーションなど、取引以外の業務プロセスにダイレクトマーケティングを導入する例も増加してきた。当時、通信販売に参入した製造業としては、2000年に「セサミンE」の通信販売を開始したサントリー・グループ、2006年にヘルスケア・化粧品の通信販売に乗り出した富士フイルム・グループなどが挙げられるが、これらの企業は自社の技術シーズを活用して開発したオリジナル商品を取り扱っている点が特徴と言えるだろう。
そして今日では、メーカー通販に替わってD2C(Direct to Consumer)という用語を頻繁に耳にするようになってきた。これは中間流通チャネルを通さずに、主に自社のECサイトを通じて製品を顧客に直接販売すること。D2Cもメーカー通販のひとつには違いないが、デジタル・ネイティブな企業が自社の主力商品そのものを通信販売するケースを指すことが多く、インターネット以前から自社製品を通信販売していた(株)ファンケルなどの通信販売会社や地場メーカーによる産地直送などをこれに含めるかどうかは、議論の分かれるところとなっているようだ。
すなわち、かつてのメーカー通販が本業の周辺領域における新規事業開発、あるいは自社の技術シーズを活用した新規事業開発としての位置付けであったのに対し、D2Cは本業の活性化を目指すものであり、製造業におけるエンドユーザーを見据えたDX(Digital Transformation)の一環と言うこともできる。逆に言えば、昨今では大手消費財製造業がDXへの取り組みを活発化しているが、その先に何らかの形でのD2Cを見据えている企業も少なくないものと見られる。
➁クリック&モルタル/マルチチャネル→ オムニチャネル/OMO:販売チャネルの拡大からCXの向上へ
2つ目のトレンドとして挙げるのは、「クリック&モルタル/マルチチャネル → オムニチャネル/OMO」である。店舗小売業による通信販売は、古くは明治時代から百貨店各社が地方顧客を対象に展開していたが、第二次世界戦後は1982年に大型店の出店規制が強化されたことに伴い、百貨店を中心に、量販店や専門店による通信販売参入が相次いだ。しかし、当時の百貨店による通信販売は、店舗販売と通信販売の経営構造の違いを理由に通信販売専門の部署を設け、店舗とは異なる商品を、異なる顧客を主対象に販売する形が中心。店舗とのシナジーは、共通のブランド・イメージの訴求など極めて限定的にしか発揮されていなかった。
一方、専業の通信販売会社による出店が加速したのは、1980年代後半のこと。当時はファッションや家具・インテリアなどの通信販売会社が、取扱商品を実際に見て、触るための拠点として出店のトライ&エラーを繰り返していた。これらは商品を直接、確かめることができない通信販売の弱点を補うことを主旨としていたが、店頭の品揃えがカタログ掲載商品の一部にとどまっていたこともあり、固定施設としての店舗がない中でのブランド戦略のひとつとしては機能しても、顧客側から見ればあくまでも補助的な手段に過ぎなかったと言えるだろう。
また、1980年代半ばには、FC方式による無店舗宅配スーパーであるフレッシュシステムズ(株)が台頭、量販店など多くの企業を加盟店に生鮮を含む食品や日用雑貨の宅配ビジネスに参入し、一躍、注目を浴びた。しかし、参入後間もなくにして撤退する企業も目立ち、その事業としての 難しさが取り沙汰されることになった。またその傍らでは、(株) ダイエー、(株)西友などの大手量販店も宅配スーパーのテスト展開を開始し、トライ& エラーを積み重ねていた。
その後、2000年代後半に入ると、大手量販店がインターネットを活用した宅配スーパーに次々に参入、ネットスーパーという用語が一躍、注目されることになった。参入企業の顔ぶれは、前出の2社に加えて(株)イトーヨーカ堂やサミット(株)などが目立ったところで、当時は店頭商品の中から宅配商品をピックアップするか、あるいは別途、フルフィルメントセンターを設けるかが活発に議論された。そしてここ数年は、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、ネットスーパーは一般生活者にとって頼りになる存在として、都市部を中心に広く社会に浸透することになった。
一方、2000年代に入ってインターネットが一般家庭に浸透し始めると、クリック&モルタル、そしてマルチチャネルが注目された。クリック&モルタルとは、オンライン上の店舗すなわちECとリアル店舗の双方を運営してシナジーを狙う手法。一方のマルチチャネルは、通信販売業界を中心に使われていた用語で、主としてカタログとインターネットを併用してビジネスを展開することを意味する。当時のこの分野のリーディング・カンパニーとしては日本ランズエンド(株)(2022年に日本から撤退)が知られているが、その米国本社では当時から、複数チャネルの併用が顧客の増大に止まらず、当該顧客の購買金額や生涯価値の底上げにも寄与することを実証していたという。
さらに2010年代初頭になると、クリック&モルタルに替わりオムニチャネルという用語が台頭し、一斉を風靡するようになった。オムニ(omnis)はラテン語で「すべての」を意味する接頭詞。これをチャネルに冠したオムニチャネルは、オフラインかオンラインかを問わず、すべてのチャネルで顧客に買い物体験を提供することを意味しており、2020年には日本オムニチャネル協会も設立された。しかし最近では、その次世代バージョンとしてOMO(Online Merges with Offline:オンラインとオフラインの融合)なる用語も台頭しており、チャネル間のシナジーを巡る議論は、その時々で 用語をリセットしながら、長年にわたり繰り返されていると言えるだろう。
こうした流れを振り返ってみると、1980年代の店舗小売業による通信販売参入が主に店舗と異なる商品を異なる顧客に販売することを、また、通信販売会社による店舗展開が通信販売のデメリットの解消や店舗がない中での信頼感の醸成を狙いにしていたのに対して、クリック&モルタル/マルチチャネルは複数のチャネルを併用することでビジネスを活性化しようという試み。そしてこれがオムニチャネル/OMOへと発展する中で、今日では販売チャネルのみならず、インターネットにより変化するカスタマー・ジャーニー全体を見据えて顧客に購入プロセスの選択肢を提供することで、CX(Customer Experience) の向上を図る方向にシフトしていると言えるだろう。
➂頒布会 → サブスクリプション:モノのコレクションからサービスの利用へ
3つ目のトレンドとして挙げるのは「頒布会 → サブスクリプション」である。頒布会は、今を去る70年近く前から親しまれてきた通信販売(無店舗販売)の1形態。月1回などあらかじめ定められたインターバルで商品を会員顧客のもとに届け、原則として毎月、代金を決済する仕組である。
頒布会の老舗と言えば(株)千趣会が想起される。同社は1954年にこけしの頒布会を手がける「味楽会」として創業、1956年に(株)千趣会として法人化された企業。全国のオフィスで働く女性を対象に、料理カードつき雑誌やハンカチ、タオルなどのオリジナル商品を頒布会形式で販売することで成長を遂げた。同社の頒布会システムは、オフィスに世話係と呼ばれるまとめ役を置き、営業担当者がこの世話係に訪問営業を行う一方、世話係がオフィスで働く会員顧客からの注文を取りまとめて同社に発注する仕組で、商品配送や月々の代金回収も世話係を通して行われていた。
また1960年代には、高度経済成長の波に乗って、洋食器や和食器のセットを取り揃える、あるいはハンカチやエプロンなど趣味の商品をコレクションするといったニーズに対応して、多くの企業が一般家庭を対象とした頒布会に乗り出した。その後、市場の成熟や物流ネットワークの整備と共にその品揃えは変化し、食品や酒類など消費財の頒布会も目立つようになってきた。そして前出の千趣会も、1976年にカタログ「ベルメゾン」を発行して品揃えを拡充すると共に、個人を対象とした通信販売へとシフトしていった。
一方でサブスクリプションは、2010年代後半に入ってブームとも言える様相を呈した概念で、2019年には(一社)日本サブスクリプションビジネス振興会が設立された。サブスクリプションはそもそも新聞や雑誌の定期購読を指す英語だが、最近になってこれが注目されたのは、経済のサービス化に負うところが大きい。この分野で先行したのは、パッケージ商品からクラウド・サービスへと変容を遂げたITのソフトウェアやコンテンツ配信などであり、これらに続いてさまざまな商品がサービス化され、ファッションやインテリアなどの有形商品はもちろん、旅行や外食などの無形商品に至るまでがサブスクリプションにより販売されるようになってきた。
すなわち、当初の頒布会がモノ不足の時代に、在庫リスクを抑えつつモノをコレクションしてもらうことを主眼に開発されたものであるのに対して、今日、日本においてサブスクリプションと呼ばれる領域は経済のサービス化の流れの中で台頭したものであり、従来、サービス商材と呼ばれていた分野までもが1回の売り切り型ではなく、一定期間の利用権として販売され、代金も年間、あるいは月々のサービス利用料として決済されていることがその特徴と言えるだろう。
「ダイレクトマーケティングのコア・コンピタンス」に続く