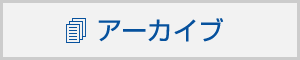2016年1月21日
前回のコラム(
南フランスお土産話①)にも書いたように、今回の旅行の目的地は、南仏はプロバンス地方にある知人が住む村。パリに到着した翌朝、パリリヨン駅よりフランスの新幹線であるTGVに乗り、マルセイユでの乗り換えを経て、計5時間ほどで最寄駅に到着。そこからさらに車で30分ほどで、山間にある人口1,000人ほどのその村に辿り着きました。
 パリ リヨン駅から南仏に向かうTGVの車内
パリ リヨン駅から南仏に向かうTGVの車内
パリから約5時間ということは、東京から新幹線で小倉に行ったようなもの。私はその村で6日間を過ごしたのですが、東京に生まれ育った私にとって、そこでの生活には驚かせられることがいっぱい。中でも最も驚かせられたのは、その村には半ば自給自足的な生活が残されているということでした。そこで今回は、私が実際に数日間を過ごした南フランスの小さな村にスポットをあてて、お土産話を披露したいと思います。
 村の中心部を臨む風景
村の中心部を臨む風景
その村には村役場、郵便局、学校、図書館、公民館、運動用のグラウンド、教会、食料品と家庭雑貨を販売するいわば“よろず屋”的小売店、パン屋、カフェ、レストランがそれぞれ1軒、半ば開店休業状態にも見えるホテルが2軒。郵便局員はたった1人で、彼が配達に出ている間は窓口業務が休みになるとか。公共&商業施設とおぼしきものはこれら十数件のみで、そこには競争とは無縁の世界が存在していました。
 村に1軒のパン屋さん。日本のブログに載ると言ったら、お客さんと一緒に喜んでポーズをとってくれた
村に1軒のパン屋さん。日本のブログに載ると言ったら、お客さんと一緒に喜んでポーズをとってくれた
1,000人ほどの住民のうち、約600人が近くにある軍の施設に勤める人々で、昔からの村の住人はたった400人ほど。彼らの住まいは、17~18世紀に建てられたとおぼしき石造りのアパルトマンや、近年になって建てられた戸建て住宅。車がようやくすれ違えるほどのメイン・ストリートと、左右に伸びる路地が織りなすその光景は、テレビで見るヨーロッパの田舎町さながらの様子でした。
 メインストリートから左右に伸びる路地
メインストリートから左右に伸びる路地
そんな小さな村のことですから、住民たちは良くも悪くも、おたがいにほぼ全員が顔見知りです。道ですれ違えば“Bonjour!”などと声を掛け合い、親しい人とは長時間にわたり立ち話に花を咲かせることに。たった数日間を過ごした私でさえも、知人とそのご近所の方々を合わせ4人ほどと食事をご一緒させていただいたので、すでに昔からの村民の1%が知り合いという計算になるわけです。
その村には既にリタイアした人々も多いのですが、敢えて言えば主な産業は農業。中でもオリーブは特産品として知られており、私もクリスマスの頃にピークを迎えるというオリーブの収穫を手伝うのを楽しみにしていました。村には個人が保有するオリーブ園以外に、村営のオリーブ園もあり、そこでは村民たちが自由にオリーブの実を収穫、自分で塩漬けにしたり、工場に持参してオリーブオイルに加工してもらったりすることができるのです。
 オリーブの実はクリスマスのころに収穫時期を迎える
オリーブの実はクリスマスのころに収穫時期を迎える
そんな村で、人々は半ば自給自足的な生活を営んでいました。私が6日間の滞在を通して食べたものにも、キジやイノシシ、ツグミなど、狩猟を趣味とするご近所の方からの頂き物がいっぱい。加えて、卵が裏庭で飼っている鶏が産んだものならば、キッチンにはトマトの水煮、キノコの酢漬け、果実のジャム、そしてもちろんオリーブオイルやオリーブの塩漬けなど、四季折々の産物を自分たちの手で加工した食品が所狭しと並んでいました。
 夏の間に収穫したトマトを水煮にして瓶詰に
夏の間に収穫したトマトを水煮にして瓶詰に
狩猟や野菜の栽培などに時間を要するのもさることながら、収穫した肉や野菜に下処理を施して家庭内に備蓄し、ある意味計画的に、日々の食卓を彩るメニューを調理するとなると、そこにはおびただしい手間と時間がかかります。しかし、村人たちはその一連のプロセスを自分たちが生きていく上で当然のことと捉え、手間や時間を厭うどころか、四季折々の営みを楽しんでいるかのようでした。
 村人が捕獲したイノシシに下処理を施した上でローストしたもの
村人が捕獲したイノシシに下処理を施した上でローストしたもの
彼らの生活は、食品の生産・加工・流通のプロセスをいわば“アウトソーシング”し、ともすれば“電子レンジでチンするだけ”という私たちのそれとは大違い。しかし、長年にわたり“仕事中心、家事は最低限”という生活を送ってきた私には、日々の生活を大切にするというこのごく当たり前の姿勢に改めて考えさせられるところがあり、私も自分のできる範囲で、日々の生活を大切にしていこうと心に誓ったのでした。