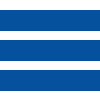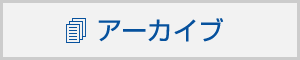2019年5月1日
最近では、都市部を中心に葬祭の簡素化が進む一方で、“〇〇さんを偲ぶ会”などの名のもとで故人の想い出を語り合う機会が増えている気がするのは、果たして私が年を取ったからでしょうか? しかし、日本料理屋の個室で、お刺身や天ぷらを肴にお酒を酌み交わし、大きな証明写真のような遺影を前に故人の想い出話に花を咲かせるというありがちなスタイルではなく、もっと故人らしい会は開催できないものか・・・。“〇〇さんを偲ぶ会”に参加するたびに、私はそんな思いを胸に秘めていました。
そんな中、折しも平成最後の日となったこの4月30日、2年前の同じ日に亡くなった親友の都合3回目となる偲ぶ会を開催するにあたって、この長年の思いをカタチにしようと、「亡くなった親友らしさを演出する」と共に、10人強に及ぶ「参加者それぞれの故人との想い出を共有する」ことを狙いに、企画から当日の運営に至るまで、できる限りの工夫を施してみました。そこで今日は、実際に私自身が手がけた事例に基づき、故人のパーソナリティを生かした偲ぶ会の企画&運営方法について、考えてみたいと思います。
まずは1つ目の狙いである、「亡くなった親友らしさを演出する」ための方法としては、あらかじめ故人の属性や趣味をリストアップするほか、Facebookグループや、対面でのヒアリングを通じて、当日参加が見込まれる仲間たちから故人らしいエピソードを募集。いくつかのエピソードが集まった段階で、幹事と料理人たちによる事前打ち合わせを開催し、ディスカッションを通じて属性・趣味・エピソードなどの中から3つのテーマを抽出すると同時に、これらをどのようにカタチにしていくかをディスカッションしました。
テーマの1つ目は、故人の出身地である北海道。打ち合わせ時には、アスパラやジャガイモ、シシャモ、ホッケ、カニなど北海道の産物、さらにはジンギスカンやザンギといった北海道の料理などをリストアップした上で、あとは料理人たちにおまかせ。料理人の1人がかつて故人と同じ職場に勤めていたこともあり、その後は彼らがメニューの試作を繰り返し、会の当日には、当初のアイデアをブラッシュアップして開発したメニューとともに、当初のアイデアをさらに広げて、故人が務めていた原宿にちなんだ料理や、故人行き付けの小料理屋の名物おにぎりをモチーフにした料理なども並んでいました。



そんなこんなで当日、供されたメニューは合計して11点(デザートの「メロン・デザートスープ」だけは写真を撮り忘れてしまいました(;゚ロ゚))。これらは前述した「北海道」「ぐるぐる」「わすれな草」の3つのテーマに基づき開発されていることに加え、故人が好きだったブラック、ブルー、ピンクをテーマカラーに設定し、例えば「北のスパニッシュオムレツ花畑」では、写真のようなピンク色のエディブルフラワーをあしらうなど、料理と飾りつけはこれらの3色を意識してトータルにコーディネートされていました。


もうひとつ、今回の会でこだわったのは、幹事や料理人など会を仕掛ける側と参加者との双方向の仕組みづくり。そもそも故人のエピソードを参加見込み者から募集したこともその1つですが、結果的にメニューに具現化されたエピソードの応募者には、当日、参加者にメニューを紹介する際に、開発の基となったエピソードを披露してもらいました。また、当日のBGMについても、故人が好んでいたアーティストのCDを持ち寄ってもらうスタイル。さらに終了後には11種類の中から満足したメニューを3つ、手挙げ方式で選んでもらい、料理人たちにフィードバックするといった工夫も施しました。そう、これにより、広義でのインタラクティブ・マーケティングとも言える、参加者との価値の共創を目指したのです。

熟年世代の方々は、これから“〇〇さんを偲ぶ会”に参加されたり、あるいは自ら主催されたりする機会も増えてくるでしょう。そんな時にありきたりな会では満足できないという方は、今回の私の挑戦を参考にしていただければ、私の往年の親友である〇〇さんも天国で喜んでくれるのではないか。そんなことを思う令和元年のはじまりなのでした。